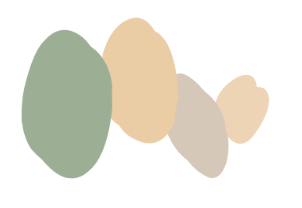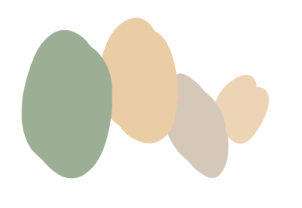EGAKUワークショップについて(更新しました)
もともと2012年の8月12日に書いたエントリ-でしたが、2014年2月24日に更新しました。
EGAKU ワークショップって何?
Human Rights Watchで働いている親友に初めて紹介された2010年から既に2年弱が経っていますが、「小さな正方形の色画用紙にドライパステルを指でこすりながら抽象画を描く・・Egakuワークショップ」にハマってます。
最近は「大人向けのアートワークショップによく行っている」というと興味を持ってもらうことも多いので、自ら10数回参加した経験を踏まえ、最近は以下の方々に特にオススメしてます。
日々仕事において左脳偏重で過ごすことの多い人
人生において「もやもや」したフェーズにいる人
自分の発信力や潜在的に有する表現力の豊かさに気づいていない人
人は皆多様であるという事実と素晴らしさを頭でなく体験で感じてほしい人
単純に楽しいことが好きな人
人に興味がある人
多様な人を集めた「真の意味で」「インタラクティブな場」を設計しようとしている人
「アート」という単語が入っているからか、「自分は絵心ないんだよねー」とか「そういう系は全然やったことない」と線引きをする人もいるのですが、個人的にはこれは多くの人が想像する「アート・美術・芸術」のものというよりは、コミュニケーションや自己理解・他者理解の文脈のワークだと思っていて、 「正しい答えの出し方を(教えてもらい)知り、努力すればよかった時代」から「正解も不正解もないものに対して、一人一人が当事者意識をもって向き合い、それぞれが納得するやり方で取り組むことが重要な時代」において、どんな人でも得るものがある学習体験だと、自分は思っています。

Egaku ワークショップは「自分は何がしたいのか」「何を大事にしているのか」「何を感じているのか」に静かに向き合う場。そしてそれを伝える表現力のトレーニングの場。他の人に、それは、どう見えているかに気付くことのできる対話の場。「自分」や「他者」に対する新たな気づきを手に入れることができる場。そんなふうに自分は捉えています。

リーダー育成、組織開発という文脈で
最近は人材育成関連の方や教育機関の方、企業の中の特定の事業部から派遣された方が参加されることも多く、参加されている方々の平均年齢は30代半ばから50代前半くらい?。社会人経験が豊富な方が参加者の多くを占めています。平日の夜7時という、日本で働くビジネスパーソンにはなかなかチャレンジングな開催時間にも皆頑張ってオンタイムでやってきて・・。
特に「リーダー育成」「組織開発」という文脈での有効性に対する認知度が少しづつ高まっているのか、日本のメディアにポツリポツリと取り上げられることも増えてきたな、と感じます。
自分もグロービスでのコンサルタントとして担当お客様企業の選抜型リーダー育成研修の設計に織り込んだ経験があります。組織のリトリート内のアクティビティ(コミュニケーションの触媒ツール)としてもぴったり(もちろん前後設計が重要)だとも感じます。
自分自身に向き合うという文脈で
そんな感じでビジネスの社会といった文脈で広がって行っていますが、多分このような経験は小中高校生や大学生・・例えば「将来これからどうしよう」「何が自分はしたいのかな」「他の人に自分のやりたいことを話す機会なんて今までなかったよ」・・そんな気持ちの若者にもいい体験になるのではないかな、と思ってます。
なぜなら、このワークショップ、自分の20代のモヤモヤ脱出のきっかけの一つとして大変お世話になったから。2010年に初めて転職をし、自分の道を模索していた時。新卒以降慣れ親しんでいた道に戻っちゃおうかな、とフラフラしていた時にたまたま出会い、10ヶ月描き続けるトツキトウカプログラムに思い切って投資してみて。
自分のモヤモヤした想いを描いてみて、自分で語ってみる。描いたものを少し距離を置いてみてみて、自分自身との対話につなげてみる。さらに一緒に参加している他者との対話からの気づきを得る。その体験を通じて「ひらめき」を得たり、新しい仲間に出会えたり、行動を起こすことのパワーをもらえたり。あの時以降の自分の人生の舵取りのあり方に少なからずのインパクトを与えた体験となった気がします。
理詰めで物事を考える傾向が強い世界にいる人こそ、頭の声で本当に自分がしたい事、好きな事が見えなくなることがあったりする。そんな時そういうノイズをシャットアウトして自分の声に静かに向き合う、「こうならなきゃいけない」という社会や周囲からの声から一旦距離を置き、自分との対話を進める。そのためにも有効な手段の一つだと感じます。
あと、瞑想やヨガなどと一緒で、継続的に習慣として描き続けるほうがその効果は高いような気がします。興味がある人はぜひ2,3回、描いてみてください。
ウェブサイト:https://egaku.co/
リーダーシップといえば。ちょうど今日、アキュメンの昨年のグローバルフェローの取材をベースにしたForbes紙の記事「The 9 Keys to Leading With Dignity」を読みました。この記事にある9つのカギ、それは:
①: Accept All
②: See Value (in another person)
③: Connect With You (before you connect with others)
④: Share The Shining Star (empower others to be the stars they can be)
⑤: Exercise Your Leadership Muscle
⑥: Tap Into Your Moral Imagination (ability to put yourself in someone else's shoes)
⑦: Create Independence
⑧: Ask (more questions and seek help, listen and learn)
⑨: Build Trust (which takes time, it is about how you do it).
EGAKUを体験した人はあのワークショップで体験することが上記の1-9全てに何らかのカタチで触れていることが分かると思います。先日読んだ記事には「リーダー教育は18歳前から」(それについては別途書きます)とあったことも合わせて、自分をリードするというセルフリーダーシップの文脈でも、他者をリードするというリーダーシップの文脈でも、対象層・年齢問わず、多くの人に体験してもらいたいな、そう感じているワークショップだったりします。
IOCA(今はELABと改称)の活動 - Egakuと社会活動
最近はEGAKU Workshopがハマりそうな組織/団体に「コラボ提案」することをプロボノで(かつリモートで)やっています。Whiteshipは営利団体ですが、同じEgaku WorkshopのコンテンツをNPO法人として提供するIOCA (Institute of Communication Arts)- 現在はELAB - が存在し、私はその関連メンバーの一人。
Egakuのコンテンツそのものにも価値がありますが、各組織のニーズや目的やその対象層となる方々の特性などを意識した前後の設計なども結構重要なので、もし、興味がある方がいればいつでもおっしゃってください。
個人的には海外での実施のお手伝いをしたい。すでに国内で英語で提供経験もあるし、異文化出身者混ぜ合わせのdiverseなグループにも何度も実施経験があるからありじゃないかな、と思ったり。
関連エントリ-:
TED絡み(ブラックさん、斎藤立さん)(EGAKUについてシグマクシスのコンサルタントの立さんがTEDに応募トークをしています)
関連エントリ-:
「止まること」と「手放すこと」(現代社会はリフレクション機会不足、そんな社会の背景にもフィットしていると感じます)
新しく何かを創るということ(ハーバードのコンペにEGAKU workshopをベースにしたアイディアで参加したときの体験)
Egaku Workshop、OpenIDEOチャレンジに(仲間がIDEO.orgのOpen ChallengeにEGAKU workshopをベースにしたアイディアで応募していました)
日本一時帰国(2013年8月)振り返り〜前半(東大のサマーイノベーションプログラムで世界から来ていた大学生と東大生に向けてEgaku Workshopを提供しました)