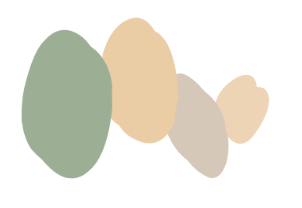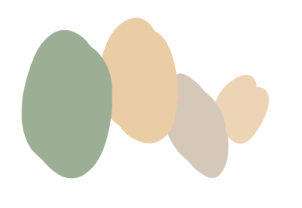ニューヨーク市で子育てしながら学んだ、現地での、3K→PreK→K(幼稚園 - キンダー)の仕組み
ニューヨーク市での子育て生活も4年半が過ぎた。
大病・怪我なく、元気に、日々遊んでいればOK!というモードで息子を育ててきたが、次第に、親として、色々な意思決定・選択をすることが求められてくるようになってきた。
保育園(集団保育)はいつからする?どこにする?何時まで預ける?ピックアップ後、子供と何する?放課後や週末は何にリソース(お金、時間、体力)かける?
といったこと。
そして、とうとう我が家にもやってきた。
K(キンダーガーデン)=幼稚園(以下キンダー)を選ぶタイミングが。
子供が5歳になる年の9月から始まるキンダー生活。その年の年始から始まるキンダー選び。
キンダーは、小学校とつながっているので(だから、K-5、K-8、K-12とこの国では言われている)それまでの意思決定よりは少しばかり重みを持った選択になる。
私立やチャータースクールに通わせる、とか、ホームスクーリングを選択する、とか、キンダーの後に別の小学校に転校する、とかもあるのだけれど、ニューヨーク市で子育てをする保護者の大半が一旦は体験する、この街の公立のキンダー選び。
今回は、その、ニューヨーク市特有のプロセスについて、まとめてみる。
*ちなみに、この国では、住んでいる州が異なると、公教育の仕組みは異なる。ニューヨーク州の中でも、ニューヨーク市(Manhattan, Queens, Brooklyn,,, etc)はウェストチェスターやロングアイランドとも仕組みが異なる。私の体験はあくまでもニューヨーク市在住者としての体験。
**また、今回の内容はパブリックスクール(公立学校)への進学の話なので、その仕組みのあり方は州や市のそのときの政策にも左右されている。今後、この同じ仕組みが続くという保証もない。あくまでも、2025年時点の話としての備忘録。
2歳まで:公的サポートがない中、なんとかする、大変な時期
まず、この街で子育てをする場合、子供が2歳までは基本的に「自己負担」でチャイルドケアを確保することとなる。
ナニーを雇うとか、近所のデイケアにいれるとか。フルタイムで親が二人とも働いていて、オフィス勤務だったりすると、ニューヨーク市でStudioや1Bedrromが借りれるのでは?というくらいお金が溶けていく。共働きの親の片方の収入がすべてチャイルドケアに消える、という家庭もあるほど。
なので「3歳までは片方の親が専業主婦・主夫か、フレキシブルワークでなんとか乗り切る」スタイルの家庭や、近所にいる、実の親・義理の親・兄妹・親族や、子育て仲間の手を色々借りながらサバイブしている家庭も少なくない。
我が家の長男のケース:2歳3ヶ月の時に、近所の保育園(私立)に入園させる。自分がフルタイムで働いていたわけじゃなかったので、支出を抑えるために、半日のみ。
朝8時すぎにdrop offで11時半にピックアップ。そのあとずっと公園などで遊ばせていた。息子に親友(私にとっての親友パパ友)ができたのも、この時期。
3歳から:公立教育の仕組みの恩恵を受けることができる
そんな、トンネルの出口に光が見えてくるのは、子供が3歳になる年の9月から。
そのタイミングで「学費無償で通える、公立の保育サービス」が選択肢に入ってくる。
「公立」として認められている場所であれば、朝8時半くらいから午後2:20pmまで、無償で子供を預かってもらうことができるようになる。2時20分以降は、延長保育分を自費で払ったり、別のアフタースクールのプログラムにいれたり、または、保護者・ナニーが子供の相手をしたりする必要はある。・・・とはいえ、2歳までよりは相当費用を抑えることができる。
公的支援、さまさまである。
ニューヨーク市の方針としては、全ての希望する3-5歳が、このサービスの恩恵を受けれるように、としてくれていて、それは素晴らしいのだけれどむち、各家庭の希望する場所のプログラムに入れるかどうかは実は別問題。
当たり前だけれど、需給の問題が存在する。
立地条件や、学校・プログラム内容、評判といった要素で、人気のところは、「希望者数>受け入れ可能数」であり「入りたかったけれど入れない」家庭が存在する。
ニューヨーク市は、この需給パズルをできるだけ効率よく、公平に解くために、抽選の仕組みを導入している。抽選はこの、オンラインポータルサイトが使われている。https://myschools.nyc/ ニューヨーク市の公立学校システムの恩恵を受けることに興味のある保護者たちは、このポータルサイトを活用した「抽選」の仕組みに、少しづつ慣れ親しんでいく。
抽選(lottery)制度:希望と運のマトリックス
子供が3歳になる年から入ることができる3K、4歳のPre K、5歳のKの子供を持つ保護者は、年始に、このサイト上で、自分たちの希望を提出する。
確か12校くらいまで出せるのだけれど、いくつの学校を記載するかはそれぞれの自由。重要なのは、希望優先順番で、それが抽選や補欠の順番結果にも影響が出る。
それぞれの家庭は、自分たちの子供の教育環境に重要なことはなんだろう?という問いに向き合いながら、口コミや、各学校の説明会での情報を総合的に判断し、希望校をリストアップする。
毎年環境が変わるのを避けたい場合は、(3Kの時は)同じところにPreKはあるだろうか、(PreKの時は)同じところにKはあるだろうか、在校生に優先的に枠が翌年与えられるか?という問いが大事になるし、通勤ルートとの兼ね合いや、我が家みたいに,2人目を抱えながら送り迎えをしなくてはいけない場合は家からの距離や交通手段を踏まえて希望を整理しなくてはいけない。
Kの時は、だんだんと「お勉強」も視野に入ってくるので、入ったキンダーの先にある小学校は自分の子供に合っていそうだろうか、なども意識するようになる。
ポータルサイト上で候補となりうる学校・プログラムを検索することができる
ちなみに、同じ学校に兄弟姉妹が通っていたり、学校の近隣に住んでいると(ゾーンと呼ばれている)抽選時に考慮される、というウェイトづけもある(実はもう少し複雑なのだけれどそれは省略 - 詳細はこちらにあるPrioritiesに関する記載参照)。
どこの学校だったら選ばれる確率が高そうか、抽選で選ばれる可能性を高めるためにどの学校を志望順位高く提出するか、そんなことも考えながら、私たちは希望校リストをポチッと提出する。
そして、春先に発表される抽選結果。ポータル上で、どの学校からオファーが来たか、どのプログラムの補欠になっているかがわかるようになっている。仲良し友達の保護者同士のチャットがその日は賑やかになる。「どこ入れた?」「どこの補欠になった?何番目?」といったように。
そして「オファーを受理します」を、ポータル上ですれば、9月からの子供の学校を決める作業は完了する。
我が家の長男のケース - 3Kのとき:2歳の時から通っていたところを、3Kの第一候補として抽選に応募(他にもいくつか近所の場所を候補には入れていた)。すでに通っている在校生が優先される、というPriorityのおかげもあって無事そのまま同じところに通い続けることができる(ただし2時20分まで)
我が家の長男のケース - PreKのとき:通っていたところが、3Kは3つ教室あったのに、PreKは1つしかないため「在校生だから翌年も通い続けることができる」前提が崩れる。同じところをPreKの第一候補として抽選に応募したものの、結果は#5の補欠。最終的に8月のギリギリのタイミングで補欠繰り上げの連絡を受け、同じところのPreKに通えることになった
自分たちがオファーを受理したとしても、色々な理由でそれぞれの家庭がオファーを辞退したり、その影響を受けて補欠繰り上げが進んだりするので、補欠だったところから夏前にオファーが来ることも珍しくはない。
K(キンダーガーテン)特有のいろいろ
3KやPreKの時とは違って、キンダーの中には、
Dual Language Program(例:英語とスペイン語のバイリンガル教育)
Gifted & Talented Program(各校独自の応用的プログラム)
を提供するところも多くあり、選択肢が増える分、親の「選ぶ力」「情報をさばく力」「自分たちにとって大事なことは何かを踏まえた上での意思決定力」などが問われるプロセスとなる。
Gifted & Talentedとはなんぞや?それってお勉強をガリガリやる感じなの?みんな子供はそれぞれ「Talented(可能性を持っている)」でしょ、なんで分けて語るのさ、とネガティブバイアスを持っていた自分も、少しづつママパパ友たちの話や学校の説明会などへの参加を通じて、自分の思い込みや感情を少し中和させていった。学校によってGifted & Talentedでやることも違うようだったし。
ちなみに、Gifted & Talentedのプログラムを抽選の希望リストに含める場合は、通っているPreKのプログラムの先生からの推薦書が必要だった。
色々なことを考慮しなくてはいけないキンダー探しは、3KやPreKより複雑性の高い道のりであった。何を知らないといけないのかがわからないところからの情報収集の旅。しかも日々で忙しく、そんなマインドスペース割けない中でやらなくてはいけない作業。
我が家の長男のケース - 2歳の時から通っていたところは、キンダーがないので、今回初めて小学校を意識した上でキンダー探しをした。全部で7つ希望を出し、4月2日、抽選の結果が出て、希望校の一つのDual Languageプログラムからオファーをもらい、他に希望していた二つのプログラムの補欠番号も5番目、9番目と悪くなかった。
子供の仲良しの3人が同じ学校からオファーをもらったみたいで、みんな同じところになったら楽しいなという気持ちが今は強い。
本当はこういうサイトとかも見れば良かったのだろうけれど、この記事を書くまでオンラインで日本語で検索することなんて思いつかなかった・・ニューヨークシティの公立学校選び: 心構え・大原則・正しい情報源 (2025年入学)
これから
こうして我が家も、とうとう「キンダー選び」を一通り終えるところまでたどり着いた。
まだ、補欠繰り上げの可能性も残っているし、近所にあるIBカリキュラムのチャータースクールの結果もまだ出ていない。Kに行ってみて、同じ場所の小学校には行きたくなくなるかもしれないし、引っ越しするかもしれない。そもそもニューヨークに何年い続けるかわからない。
なので、今回のキンダー決めが終わっても、自分たちの選択や選択肢を振り返る機会は定期的に訪れるのだろう。
とはいえ、「選ぶ自由」と「多様な価値観を考慮した、できる限り公平さを担保した機会分配の仕組み」を、今回、親として体験できたのは楽しかった。
長男は9月から、どんな環境で、どんな仲間達に囲まれて学ぶのだろうか。
楽しみである。
そして、これから我が家は、0歳である二人目のチャイルドケア確保という、新たなパズルに向き合っていく時期に入っていく。
関連エントリー