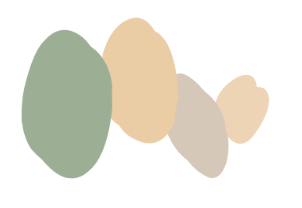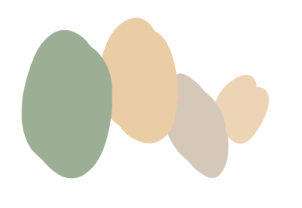その反応、誰の声?——トリガー (trigger)とエゴ(ego)の交差点で立ち止まる
2018年に書いた、「自分にとってのトリガー(trigger)を理解する」というエントリー。誰しもが持っている、つい心がザワっとする“カチンとくるきっかけ”。
それに気づくこと、言葉にしてみることが、自己理解を深めるうえで、そして、他者と関わるうえで大切な入口になるという内容だった。
あれを書いたのは、Acumenでリーダー育成プログラムをデザインしている時。
あれから少し時間がたち、そのtriggerについての理解が、ある学びを通じてもう一歩深まった気がする。今回はそのことについて書いてみようと思う。
きっかけは、このブログでも何回か書いている、Upbuildのコーチングトレーニングプログラムでの学び。
そこで出会った、こんな概念。
ego = ”false sense of identity of who we think we should be”
TriggerとEgo — この2つは、自分たちの“反応”の背景で密かに絡み合っているようなもの。最近は、triggerされて、平常・穏やか・前向きな状態が揺さぶれるたびに「これはegoの声かも」と思うようになった。
そんな今の視点から、triggerとegoの関係を、自分自身の体験も交えて少し整理してみたい。
エゴ(ego)とは何か?
多くのコーチングトレーニングプログラムと同様に、Upbuildでも、「コーチとして成長するための学びを得るためのプログラム」=「自分という一人の人間に深く向き合う時間を与えられるプログラム」となっている。
その、自己理解を深める切り口としてエゴ(ego)の概念を教わった。クライアントに向き合うコーチとして自分自身のエゴに自覚的になることも大事だし、クライアント本人のエゴが本人を苦しめているという構造を見極める力も大事ということで。
そんな背景でUpbuildが共有してくれたegoの定義
Ego = “false sense of identity of who we think we should be” “identities who we think we should be”
「自分はこうあるべき」「こう見られるべき」——そう思い込んでつくり上げた“偽りの自己像”のこと。
最初にこの定義を聞いたとき、正直ちょっとモヤモヤしたのを覚えている。
「こうあるべき(should)」と「こうありたい(want)」のあいだって、どうやって見分けたらいいんだろう?“「理想の自分」や「ありたい自分像」を具体的に持つのは、目標達成に向けた原動力になるので大事なこと。努力して何かを目指すこと”と、“Egoに突き動かされて頑なになること”は、どう違うんだろう?
最初は、そこがあまりうまく整理できなかった。
でも、時間をかけて自分のtrigger体験を振り返るうちに、少しずつピンとくるようになってきた。
ここで登場するエゴは、別に持つことがいけないものではないのだけれど、それが自分のbeing/doingに与えている影響に気をつけなくてはいけない、そんな存在なのだ。
例えばコーチとしての自分としての文脈でいうと、自分のエゴは
クライアントにとって価値ある時間を提供できるコーチというアイデンティティ
インパクトのある「問い」を投げることができる存在
豊富な知識やリソースを持っていて、何かあれば相手を支えられる人間
というものがある。こうありたい、はもちろんだけれども、コーチとして活動するならこうでなければ、というものと重なっている。「〜するなら・・こうでなければ」は私たちの世界に溢れていて知らぬ間に自分達も吸収しているものだ。
だからセッション中、または営業中などに、「今の問い、微妙だったかも?」「この時間、本当に役に立ってる?」という不安がよぎると、心がざわつく。平常・穏やか・前向きな状態が奪われる。トリガー反応の登場で、本来の、のびのびとした自分の良さが出ている状態のコーチから、緊張感のある硬いコーチになってしまう(と少なくとも自分は思う)。
そんな風に、あまり望ましくないトリガー反応の裏には、「ちゃんとしたコーチとしてこうあるべき」という自分のegoの声がある・・・という捉え方ができるのだ。
トリガー反応の裏に潜むエゴ(ego)の声
二つさらに具体例を。
仕事バージョン:
ある大事なプロジェクトの締切が迫っていたときのこと。信頼しているチームメンバーの判断に対して、強くイラッとする気持ちが湧いてきた。 「もっと早く決めてくれていれば…」「今その言い方する?」と、頭の中で反芻してしまう。
その裏側にあるのは 「クライアントや最終的な受益者にとって、最もよい形で価値を届けたい」 「そういう人間でありたい、そういうチームの一員でありたい」という自分の理想像。
チームメンバーの行動が、その理想像・egoをぐらつかせる。 「私たちは本当にちゃんと価値を届けられるのか?」という焦りや不安が湧いてくる。egoが「その理想像が崩される」と感じ、反応する。他責モードという、あまり望ましくないトリガー反応が現れる。
家庭バージョン:
子どもに対して、「のびのびと学んでほしい」 「自分の“好き”を見つけてほしい」 「いろんな経験をしてレジリエンスを育んでほしい」という願いがある。そしてそれと同時に、 「そういう環境を選び取れる親でありたい」 「子どもの人生にプラスの影響を与えられる親でありたい」という自己像も、自然と内側に育っている。
一方で現実がうまく噛み合わない場面で、たとえば「こういう体験をさせてあげられなかった」と感じたときに、その出来事の要因に対して、つい他責の感情が浮かんできてしまうことがある。誰かの判断や環境のせいにしてしまいたくなる気持ち。これもあまり望ましくないトリガー反応。
でもそれは本当の意味で怒っているというより、「こうありたい」という親としての自分のegoが傷ついて、反応しているだけなのかもしれない。
triggerの奥を見る問い
これらのどのシーンでも、理想像に対する執着が強いと、現状とのギャップに対して敏感になりすぎてしまうことがある。
triggerされたときに、つい外に向かって反応してしまう。「あの人のせいで」「あの対応があり得ない」「環境がよくなかった」と、原因を外に求めたくなる。
でも少し落ち着いてから振り返ってみると、「この感情、どこから来てるんだろう?」と自分に問い直すことができる。そうすると見えてくるのは、「本当はこうありたかったのに」「こういうふうに評価されたいのに」という、“自分の理想像”に対する強い思い。
そして、それが揺らぐことで、egoがざわつき、triggerが引かれていたという構図。
そのことにUpbuildで気付かされてからは最近は、triggerされたとき・反応を自覚するときに、こう問いかけるようにしている。
「今、私の中のどんな“should(〜であるべき)”が傷ついたんだろう?」
「理想の自己像・アイデンティティに執着しすぎていないだろうか?少し握っている手を緩めたらどういう世界が開けるだろうか?」
「自分は(egoにコントロールされている・振り回されている)今のような状態の自分でいつづけたいんだっけ?」
そういった問いを頭に浮かべることで、怒りや不安といった“感情そのもの”に巻き込まれる度合いが、ある程度健全なレベルに落ち着き、それをきっかけに自分の価値観や願いに立ち返ることができるようになった気がする。もちろん他者との関わり方にも大きな違いが生まれる。
私たちは日々、いろんなことにtriggerされる。誰かの言葉に、行動に、態度に、または思うようにいかない状況に。
でも、その反応の奥には、自分の中の「こうあるべき」や「こう見られたい」という理想像——つまりegoがいることがある。そういったegoを排除する必要はないし、triggerを感じない人間・完全無反応の人間になることがゴールでもない。
むしろその反応は、「何かが引っかかっているよ」「ここに大事なものがあるよ」と教えてくれるサインのようなものなのだと思う。
「自分の中の何が大事で、それがどのように守られたいと思っているのか」そんなことに立ち戻るための入り口として、自分との大切な対話のきっかけとしての貴重なもの。
と同時に、自分の大事な人が、その人らしくない言動(トリガー反応)をしているシーンに出会ったら、「今、あの人の中のどんな“should(〜であるべき)”が傷ついたんだろう?」と想像できるような心持ちでいたい。そう思ったりする。
が、それも自分のegoであろう。執着しすぎない距離感を大切にもしたい、笑。
関連エントリー:
自分にとってのトリガー(trigger)を理解する - 2018年11月
ゴットマン博士による「関係性を破壊する 4つのコミュニケーションの悪癖」- 2021年9月
「嫉妬」との向き合い方 - 2018年3月
#009 - 食事の準備というeveryday task - "what's for dinner?" 対策 - ポッドキャスト
#044 - 【まなびあいシリーズ 】Upbuildコーチングトレーニング体験談 - ポッドキャスト
ポラリティマネジメントと、アウフヘーベンする、と色々。- 2024年4月