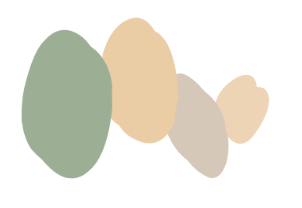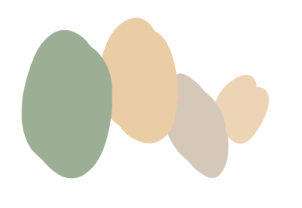Sesame Workshopについて
前回書いた「冬期集中講座『Informal Learning for Children』」を通じて、いろいろと発見があったので、少しずつアップデートしていきたいと思っています。今回は、この2週間で自分に多大な影響を与えている Sesame Workshop について。
Sesame Workshopについて発見したこと
まず「そもそも」の話で、自分にとって完全に New! だった気づきをリストアップ:
実は、セサミストリートの産みの親である Sesame Workshop は NPO(非営利団体)。
40年以上前の発足時から、子どもの教育へのインパクトをミッションに掲げていた。
Sesame Workshop が制作するコンテンツは、5歳以下の子どもを意識したものが多い。
アカデミックな研究と制作現場側のコラボの徹底(おそらく世界一)。
制作コンテンツは以下の3つのテーマにフォーカス(※2013年1月時点):
健康
リテラシー(数字やABCのみならず、幅広い! 最近は米国ではSTEMがブーム)
※STEM = Science, Technology, Engineering, Math。これに Art を加えて STEAM というプログラムも展開され始めてます。感情
自分の中では「2. リテラシー」のイメージが強かったけれど、実は「1. 健康」と「3. 感情」の力の入れようも半端ない。
特に「感情」については、ポジティブなもの(自分を知る・他人と関係を築く social/emotional スキル)だけでなく、親子で会話するのが難しいトピックにも積極的に取り組んでいる。
例えば「親の死」について(以下のYouTubeはその短縮版)。他にも、経済的不安・離婚・徴兵などのプロジェクトもある。
常に時代の変化を意識して進化し続ける Sesame Workshop
テレビの普及度が今ほど高くなかった時代に始まった Sesame Workshop。もちろん時代の変化とともに発信媒体の多角化も続けている。
そして「Formative Assessment」といって、制作過程にユーザーを巻き込んでリサーチを行い、制作内容に結果を反映させるプロセスを大事にしているのも特徴。
Sesame Workshopと日本と世界
現在は150カ国に対して何らかの形のセサミストリートのプロダクションを届けていて、そのうち30カ国には「共同制作」という形で、現地の文化・教育のあり方・教育ニーズに合わせた独自のコンテンツを展開中。
日本では、長年(1970年代から)NHKでアメリカ版のオリジナルを放映していた。でも、Sesame Workshop が共同制作を持ちかけたときに NHK が断ったという経緯があったらしい(なんと!)。
その後「セサミストリート・パートナーズ・ジャパン」という組織が発足し、改めて Sesame Workshop と共同制作を行ってテレビ東京で放映。しかしこれは2004〜2007年で終了、その後同組織は解散(悲しすぎる…&知らなかった!)。
今は衛星かケーブルでオリジナルの英語版を見られるはず。Sesame Workshop の人に聞いたところ、「日本の人たちはセサミを “英語教材” として使うと認識している」とのこと。…もったいない…
セサミを知らなかった自分
キャラクターがあまりにも有名だったため、私は完全にディズニーと同じような位置づけのコンテンツだと思っていた。だから、自分は明らかに「セサミストリートで学ぶ機会を十分に持てなかった日本人」の一人。
(記憶にあるのは「おかあさんといっしょ」「ポンキッキ」→「こどもチャレンジ」)
今受講している「Informal Learning for Children」のクラスは100人以上が参加していて、アメリカ人が多い。セサミで育っていない学生は、私を含めて片手で数えるほどだった。
世界の標準になりつつあるセサミ
セサミストリートは進化を続け、今や「グローバルスタンダード」になりつつある。特に南アフリカやバングラデシュなど、発展途上地域における教育的インパクトは目覚ましい。
今までこうした世界をまったく知らなかった自分。
だからこそ、もっと多くの人にこの発見を共有したいと思っています。